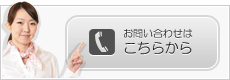MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.17

実効税率ってなに?
最近、巷で「税制改正により減税された関係で、実効税率がかなり下がるそうだよ。」「税効果会計を採用するには実行税率を計算しなければならないよ。」などという話が聞かれます。そこで、この「実効税率」とはどのようなものなのかについて簡単に説明します。実行税率とは
企業が負担する税金には様々なものがありますが、この中で主要な税金である法人税・住民税(法人税割)・事業税についてトータルでいくら負担しているのかを示す比率(税前利益に対する比率)が実効税率なのです。
例えば実効税率が41%という場合は、「法人税・住民税(法人税割)・事業税の合計した税額は、税引前利益の41%に相当する。つまり、税引後利益は税引前利益の59%(100%-41%)になる。」ということになります。
実効税率の計算式
実効税率の種類
実効税率は上記の計算式によって算出されますが、計算の基礎となる税率は、企業規模、所在地、課税所得の大小等の理由により異なるため、使用する税率によって実効税率も様々になります(下記参照)。
この中で一般的に利用される代表的なものは、標準税率を使用して算出されます。
実効税率の具体例(平成11年税制改正時点)
標準税率を使用
法人税=30.0%、住民税=17.3%、事業税=9.6%
実効税率=(30.0%*(1+17.3%)+9.6%)÷(1+9.6%)=40.87%
中小企業(資本金1億円以下)で所得400百万円以下の場合
法人税=22.0%、住民税=17.3%、事業税=5.0%
実効税率=(22.0%*(1+17.3%)+5.0%)÷(1+5.0%)=29.34%
よって、実効税率といっても、その値は企業の状況等により異なりますので、状況判断による使い分けが重要になるのです。