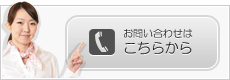MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.15
経営分析のすすめ(3)-「ROE」株主資本利益率

この「目標」の1つとして「経営指標」が挙げられます。
経営指標には、売上高利益率・株主資本比率・総資本回転率など様々な「切り口」(分析)があります。
その中で、最近注目されているのがROE(Return on Equity … 株主資本利益率)であります。
ROE(Return on Equity … 株主資本利益率)とは
「売上高至上主義」の経営が長い間行われ、経営指標の中でも売上高や利益を重視する傾向が強く、企業が有する資産や負債はあまり重視される傾向にありませんでした。
ところが、最近は単に収益性や成長性だけでなく、「投下した資本」に対しての収益性や成長性を考慮した「資本の運用状況」(株主価値)を重視する経営が重要視されてきています。
そこで、企業の「資本の運用状況」を的確に表示するROEが注目されているのです。
ROEは、次の算式で計算されます。
また、次の様に分解し説明できます。
ROEの活用
ROEは、上記の様に3つの指標から構成されており、単に「売上高の増加」「利益の増加」が必ずしもROEの上昇に連動していません。
ROEを上昇改善するには、「売掛金の回収期間を短縮し、経営資本(資産)の運用効率を上昇させる(総資本回転率の上昇)」「少ない投資で多くの売上高を獲得する(総資本回転率の上昇)」「コスト削減(変動費・固定費)により利益率を上昇させる(売上高純利益率の上昇)」などの複合的な経営戦略の実現が要求されるところに、この指標の優れた点があります。ただ、「借入金(有利子負債)の増加」がROEの上昇になる場合もあり、有利子負債の上昇は企業環境の変化に迅速に適応する能力の低下となりますので、ROEが財務上のリスクを十分に説明できないという限界があります。
つまり、ROEが経営状況の全てを表す「万能の指標」であるのではなく、あくまで「経営状況を的確に表す重要な経営指標の1つ」であることに留意し、企業の「目標」として利用することが最も大切であるということなのです。