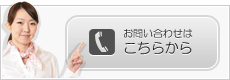MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.14
経営分析のすすめ(2)-限界利益と損益分岐点
限界利益とは
「収益(売上高)」マイナス「費用」で表される「利益」の1種類であり、
「売上高」-「変動費」=「限界利益」
「限界利益」÷「売上高」=「限界利益率」
で計算され、→ 売上高が増加すれば限界利益も増加する。商品・製品1個(1円)当たりの獲得する利益額=限界利益率といえます。
また、「利益」+「固定費」=「限界利益」でも計算されることから、
→ 固定費が増加すれば限界利益が増加することから、固定費を負担する能力の度合いといえます。
変動費・固定費とは
企業活動において発生する「費用」は、「変動費」と「固定費」に大別されます。
「変動費」 … 材料費・運送費など売上高に比例して発生額が変動する費用
「固定費」 … 人件費・家賃など売上高に関係なく固定的に発生する費用
損益分岐点(売上高)とは
「収益(売上高)」-「費用」=0、つまり「利益」=0となる売上高です。
限界利益との関連では、「固定費」÷「限界利益率」で算出されます。
経営分析の具体例
平成11年度
A社;売上高 100、変動費 60、固定費 20
B社;売上高 100、変動費 20、固定費 60 とする。
限界利益、限界利益率
A社;利益=100-(60+20)=20 限界利益率=(100-60)÷100=40%
B社;利益=100-(20+60)=20 限界利益率=(100-20)÷100=80%
つまり、A社・B社とも利益(業績)は20で同じですが、限界利益率は大きく相違しています。
平成12年度ここで、大幅減収し70になる場合と大幅増収し150となる場合に、両社の利益(業績)がどのようになるのか予想計算してみます。
売上高=70の場合
限界利益 固定費
A社;(70×40%) - 20 =8(黒字)
B社;(70×80%) - 60 =△4(赤字)
つまり、売上高は同額(減少)でも、利益はA社=黒字、B社=赤字決算と、大きく業績が相違しています。
売上高=150の場合
限界利益 固定費
A社;(150×40%) - 20 =40(黒字)
B社;(150×80%) - 60 =60(黒字)
つまり、売上高は同額(増加)でも、利益はA社=40の黒字、B社=60の黒字決算と、大きく業績が相違しています。
分析結果この理由は、損益分岐点と限界利益率により理解できます。
損益分岐点(売上高)
A社;20÷40%=50 … 売上高が50まで減少しても赤字ならない。
B社;60÷80%=75 … 売上高が75未満となると赤字になる。
限界利益率
A社;40÷100=40% … 売上高の40%しか限界利益とならない。。
B社;80÷100=80% … 売上高の60%は限界利益となる。
以上から、両社の「特徴」は、以下の通りといえます。
A社 ; B社に比べて「材料費、外注費などの変動費が高い。」ため、限界利益率が低く売上高が増加しても思うように利益が上がらない。
その一方で、「人件費などの固定費が低い。」ため、売上高の減少(不況)に対して強い企業体質である。
B社 ; A社に比べて「材料費、外注費などの変動費が低い。」ため、限界利益率が高く売上高が増加した場合大幅な増益となる。
その一方で、「人件費などの固定費が高い。」ため、売上高の減少(不況)に対して弱い企業体質である。
「限界利益」「損益分岐点」から企業の特徴を把握することは経営戦略上重要であることが、理解いただけたと思います。