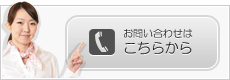MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.12
管理会計のすすめ(2)
「決算書の再考」からスタートしよう。まずは、「管理会計」の第1歩として、企業が作成している決算書の内容の再考から、スタートします。
会計業務(作成している決算書)の現状
中小企業の多くは、以下の様に大別して月次決算と年次決算の2種類の決算書を作成しています。
・月次決算
毎月の業績を適時に把握するため、その月に発生した取引データを処理し、年次決算書に比較して簡便的な決算書を作成しています。
・年次決算決算月に合せて税務申告、株主・出資者への報告(株主総会、社員総会)、取引金融機関への報告などから、毎年1回決算が必要であり、この年次の決算書を作成するために、日々の取引データの処理と減価償却・実地棚卸など決算特有の処理が行われています。
何が問題なのか?何が不足しているのか?
・月次決算
月次決算の目的が、年次決算の前段階(年次決算書作成のための月次決算書作成)に終始しており、「企業の現状を正しく把握し、経営に役立つ情報」(管理会計)となっていないケースが多くあります。
・年次決算税務申告、外部関係者報告用の資料として作成されるため、決算書が「1年間の業績を集計した単なる結果」を示すものにしかなっていないケースが多くあります。
どうすればよいのか?
「企業の現状を正しく把握し、経営に役立つ情報」(管理会計)とするためには、情報としての精度向上、スピードアップと分析資料の充実が重要になると考えます。
月次決算が年次決算の基本になるためにも、月次決算の精度向上、スピードアップと分析資料の充実を優先的に実施するのが効果的といえますので、月次決算について主な点を列挙します。
・月次決算
精度向上
(1)売上と原価の対応 … 売上計上日とその原価計上日の整合性の確保。棚卸による在庫確定。
(2)経費の期間対応…費用発生日の把握(請求書の締め日の統一)。
(3)預金・現金・借入金残高の確定…通帳等との整合性確保。
スピードアップ
スケジュール管理、役割分担の明確化、作成資料の定型化など月次決算を行う体制の整備が重要です。また、外部に記帳代行を委託している場合は、その委託業者を含めて検討することが必要です。
分析資料の充実

基本となるのは、「今月はどのように変化したのか?」であり、今までの実績の推移から、単月・累計ベースでの前年比較検討が重要になると考えます。そして、前月、前年同月との相違を正しく把握・認識して、その原因を追求し、対策を検討する資料として役立てることが、「管理会計」の第1歩につながっていくのです。
(1)売上高、売上原価、粗利益の比較、分析
(2)経費の比較、分析
(3)資金(キャッシュフロー)の動きの比較、分析