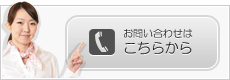MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.11
管理会計のすすめ(1)
なぜ、今「管理会計」なのか長期景気低迷にあえぐ経済社会において、「規制緩和」「グローバル化」のもと企業を取巻く社会・経済環境は激変しています。この構造的変革は、企業間の競争をより促進し「優勝劣敗」の構図がますます浮き彫りとなることから、この変化を素早く把握・認識し適切に対応する企業しか生き残れないと考えられています。
そこで、自社の現況を正確に把握・チェックし、環境変化に常時照らし合わせながら経営判断を行うために、業績管理体制の確立による「管理会計」の導入が、今求められていると考えます。
管理会計と財務会計
企業会計は、その目的により税務署、金融機関等外部報告用に法令に基づき作成される「財務会計」と、企業内部の業績管理目的に作成し経営者の意思決定に利用される「管理会計」に分類されます。両者は同じ資料から作成されることが多く、互いに有機的に結合しているのですが、その目的が違うことから、その役割も大きく違っています。

しかし、その一方で経営者がこの決算書を利用して何らかの経営判断・意思決定を行うには不充分であるケースが多いのです。
管理会計とは
経営者の経営判断及び意思決定に対して、有用な会計情報を迅速に正確に提供する会計制度であるということができます。
具体的には、
部門別製品別利益管理 … 「どの部門で、どの製品で、どの程度の原価が発生し、また利益を生み出しているのか?」「逆に不採算な部門、製品はなんなのか?」
短期経営計画 … 「現状の業績、見込みからいくと、来年の業績はどうなるのか?」
投資の意思決定 … 「新機能の機械設備を導入したいが、採算はとれるのか?」
など経営者の知りたいことについて、的確に迅速に会計的な情報を提供するのが、「管理会計」の役目なのです。管理会計を導入するには
管理会計の重要性は認識していただいたと思いますが、では今日からすぐに実施できるかというと、簡単に行かないのが現実です。

そのためには、徐々に段階を踏みながら「実績の把握」「計画(PLAN)」「実施(DO)」「検証(CHECK)」「見直し(FEEDBACK)」の手続きを繰り返すことにより、より正確な、役立つ情報が入手できるようになるのです。
まずは、現状作成している「決算書」の内容の再考から、スタートしてください。